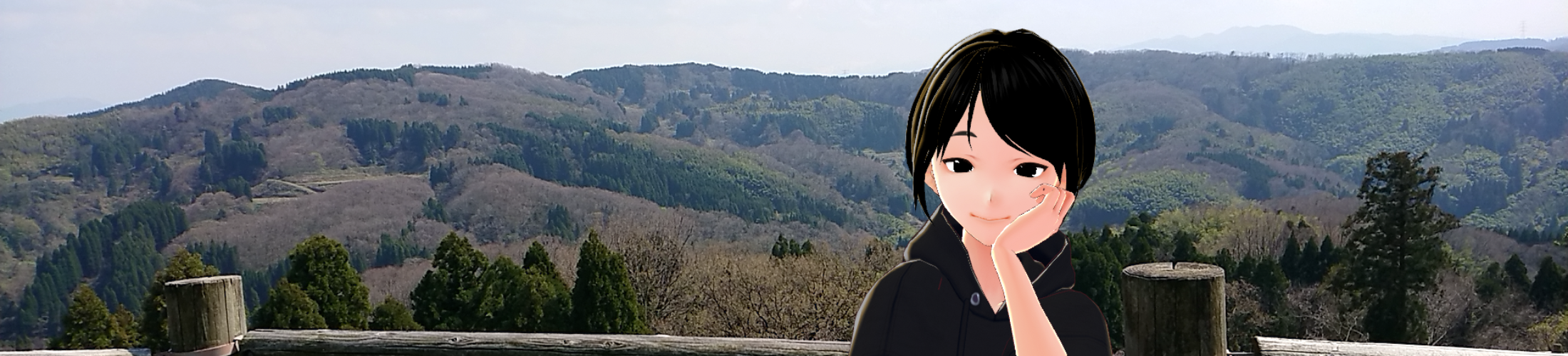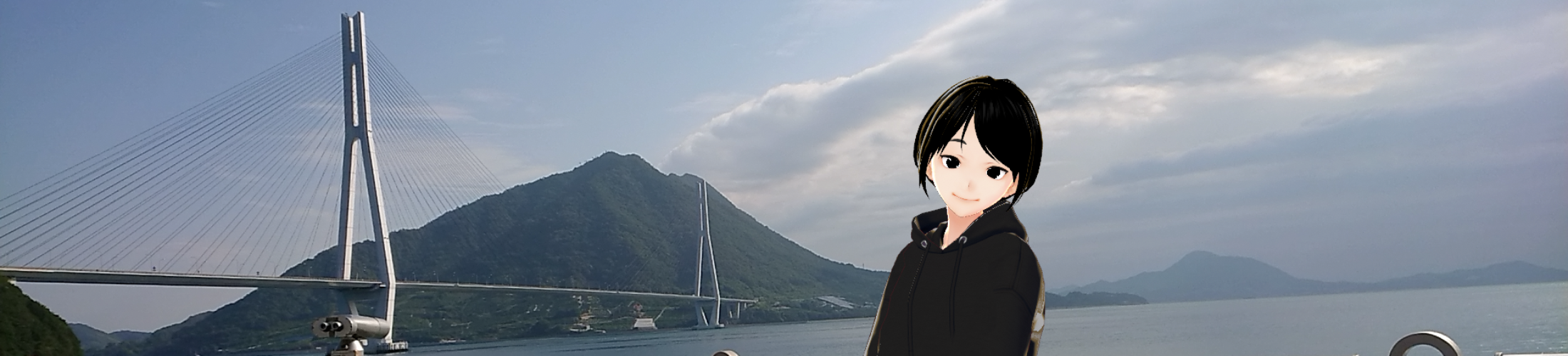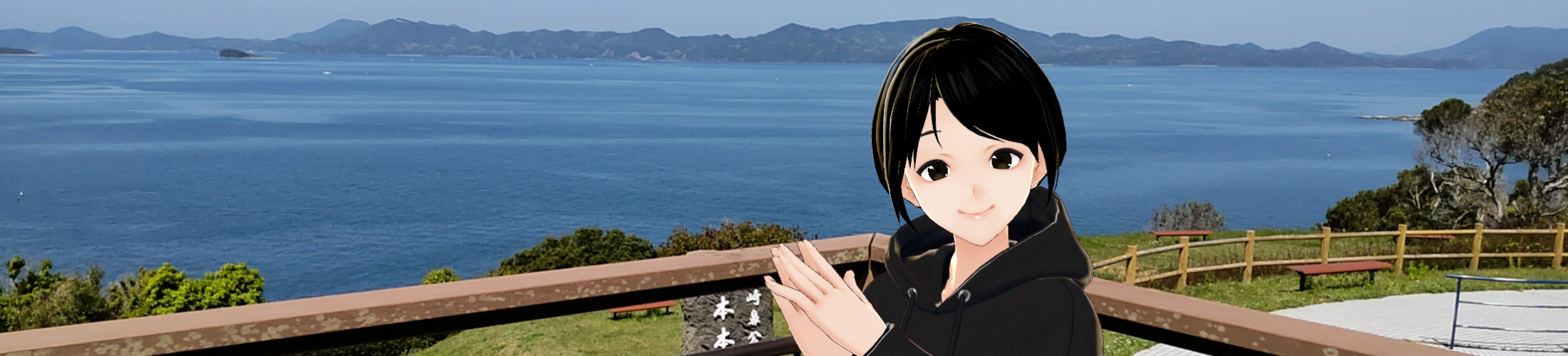バイクに乗ってみたいけど自分でも免許取れるのかな?と心配しているおじさんがいるならば、伝えてあげたい。

自動二輪免許を取得するための教習ってどんな内容のか?アラフォーのおじさんは実際どんな感じだったのか?
まずは第一段階について実体験を元に紹介します。
バイク教習は二段階ある
自動二輪の免許は、二段階に分かれます。それぞれ必要な教習時間(最短)は以下のとおりとなっています。
| 取得する免許 | 普通自動車免許 | 第一段階 | 第二段階 | 技能教習合計 | 学科 |
| 小型自動二輪 | 無し | 6H | 6H | 12H | 26H |
| 有り | 5H | 5H | 10H | 1H | |
| 普通自動二輪 | 無し | 9H | 10H | 19H | 26H |
| 有り | 9H | 8H | 17H | 1H | |
| 大型自動二輪 | 無し | 16H | 20H | 36H | 26H |
| 有り | 14H | 17H | 31H | 1H |
第一段階の教習の最後に「みきわめ」というものがあり、これをクリア=必要な技術を身に付けたと判断されると第二段階に進めます。
第二段階の最後にもみきわめはあり、これをクリアすると卒業検定を受けることができます。
上記で最短と書いたのは、みきわめに落ちる場合もあるためです。その際は補講を受けることになります。
では、普通自動二輪の第一段階の教習内容について見ていきましょう。
ちなみにわたしは普通自動車免許ありだったので、第一段階は技能教習のみで学科はありませんでした。
<関連記事> 自動二輪免許を取得するために教習所に通うおじさんにとって直面するのはどれくらいのペースで通うかという問題ではないでしょうか。 例えば一般的なサラリーマンであれば、平日昼間は仕事があるため通うのが困難と ... 続きを見る

12:二輪免許取得にかかった日数と、技能教習は短期集中で行けという教訓
第一段階の教習内容
第一段階の教習内容は、バイクの基本的な操作の習熟と共に、「課題」を通じた技術面の練習になります。
序盤
まずはバイクを最低限動かせるようになるための基礎として以下を練習します。
発進・停止
バイクの発進と、ブレーキを使って停止する練習を行います。
最初は短い距離・低速での発進・停止を繰り返し行い、慣れてきたところで長い距離での発進停止とレベルアップしていきます。
ギアチェンジ
慣れてきたら、ギアチェンジの練習を行います。
自動車のマニュアル車を運転したことが無い人には半クラッチの意味するところや感覚がつかみにくいかもしれません。
加速・減速
教習所の中とは言え、ある程度スピードを出せるようになっていなければなりません。
短いコースかもしれませんが、40km/hは出せるようにしておきましょう。
しっかり加速できないと後々で苦労します(急制動とか)
中盤~終盤
基本的な操作を身に付けたら、次はバイク教習の「課題」というものを練習していきます。
課題とはつまり、卒業検定で実施する内容ということです。
スラローム ・・・早く曲がる練習
グネグネと左右に車体を素早しく切り返しながらパイロンの間を通ります。
卒業検定では普通二輪で8秒以内、大型では7秒内の通過が規定タイムとなるので、スピードも必要となってきます。
最初は結構恐怖心が出ましたが、慣れると楽しいものでした。
一本橋(平均台) ・・・低速でバランスを取りながら走行する練習
長さ15m、幅30cm、高さ5cmの平均台をなるべくゆっくり通過する課題です。
卒業検定では普通二輪で7秒以上、大型二輪で10秒以上が規定タイムとなります。
これはかなり苦労しました。まず最初はそもそも台に乗れなかったんですよね。
クランク ・・・低速で曲がる練習
以下の画像のような狭いコースを通ります。

低速で曲がるため、スラロームとは必要な技術が異なります。
わたしはこれが一番苦労しました。軽く10回はここで転倒したと思います。
八の字(S字) ・・・滑らかに曲がる練習
八の字もしくはS字を描いて走行するだけで、課題の中では1番簡単です。
特に苦労はしませんでした。
坂道発進 ・・・坂道で後ろに下がらず発進する練習
ブレーキと半クラをうまく使えれば問題なし。
特に苦労はしませんでした。
振り返り
以上が第一段階の教習内容になります。
こうして見ると低速系の課題(一本橋、クランク)が苦手だったことがわかりますね。
わたしは何回も転倒しましたが、第一段階は一発でみきわめをクリアできました。
通った日数としては5日間です。
しかしまったく安心はしておらず、途中で動画やら本やらで勉強し始めていました。
でも、不安と同時に「俺ってバイク乗ってるぜ~」みたいな変な高揚感があって非常に楽しかった記憶があります。