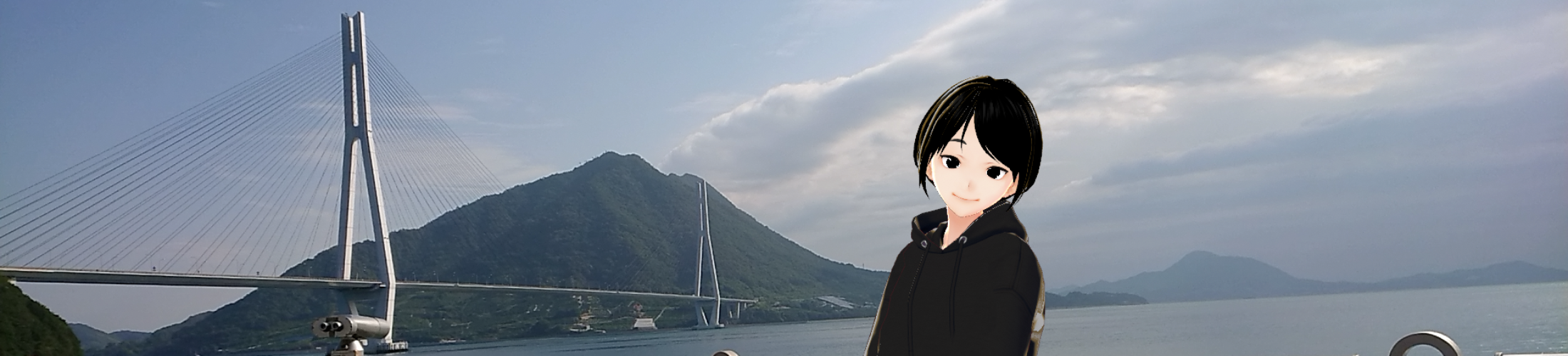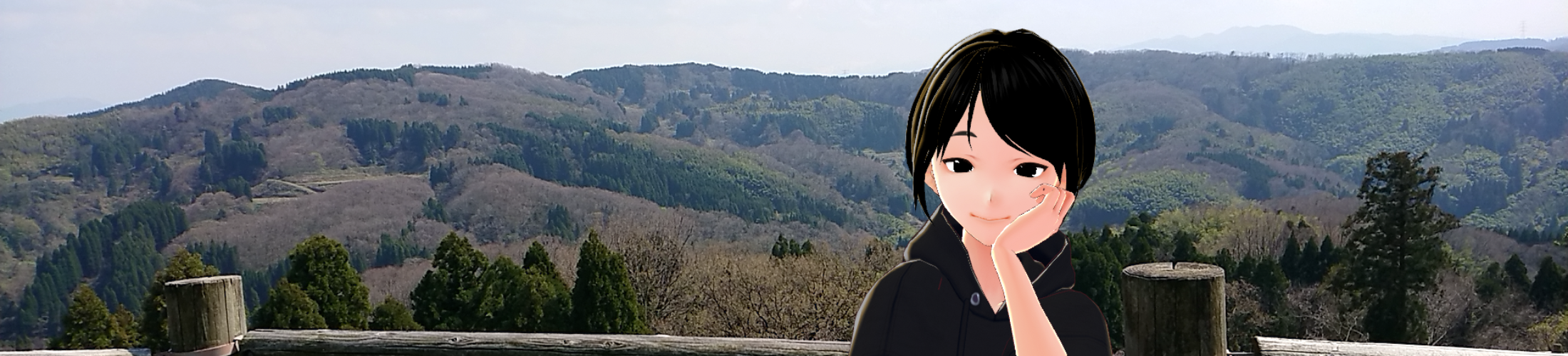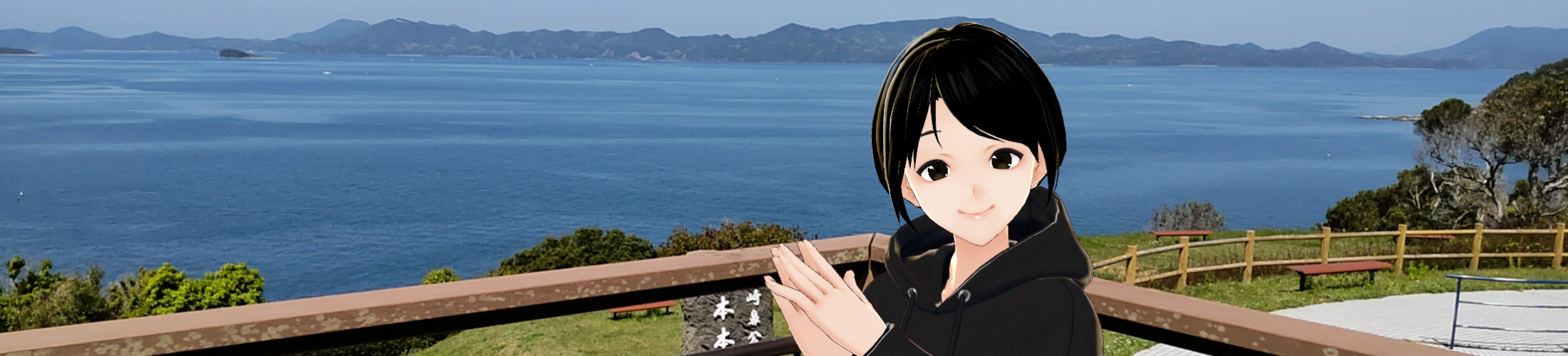世の中には申請することでお金がもらえる制度があります。
その中でも身近なものが「医療費控除」です。
なんだか難しい字面ですが、簡単に言うとこういうことです。
- 医療費がたくさんかかって苦しい時は税金を安くしてあげるよ。
- いくらかかったのか申請してくれたらもらい過ぎた税金を返してあげるね。
ここでの医療費がたくさんの目安は、1年で10万円以上と覚えておいてください。
わたしはこれまで幸いにも医療費が10万円を超えることはなかったのですが、昨年、子供の歯列矯正で50万円ほど支払いがありました。
これを医療費控除申請し、実際にお金がもらえた(税金が戻ってきた)ので、やり方を紹介します。
医療費控除はやらないと損ですよ!

※本記事では、わかりやすさを優先した説明としているのでご了承ください。
目次
医療費控除とは
国税庁のサイトに以下のとおり説明があります。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
「所得控除を受ける」とどんなメリットがあるのでしょうか?
所得控除を受けるとはどういうこと?
給与等の収入があった場合は、税金(所得税、住民税等)を支払います。国民の義務です。
この税金をいくら支払うのかの計算の元となるのが「所得」です。
税金は所得×○%(所得税率)として算出するので、所得が低いほど税金は安く済むことになります。
超ざっくりと、収入と所得の関係を以下に示します。
収入から「所得控除」を引いたものが所得です。
つまり、所得控除を受ける(大きくする)ことで、所得を減らす=支払う税金を減らすことができます。

医療費控除のメリット
医療費控除により所得を減らすと、そこから算出される税金を減らすことができます。
収入(給料)が同じなら、納める税金が少ない方が自由に使えるお金は大きくなりますね。
メリットが生まれるのは所得税(国)と住民税(地方)になります。
- 所得税:還付金(納め過ぎた税金を返してもらう分)がもらえる
- 住民税:翌年度の住民税が安くなる
例として、医療費控除を申請した場合のイメージを図に示します。

医療費控除によるメリットを理解いただけたでしょうか。
かかってしまった医療費は仕方が無いので、医療費控除の制度を使って少しでも得になるように持っていきましょう。
歯列矯正は医療費控除の対象になる?
まとまった医療費がかかるものの代表が子供の歯列矯正ですが、結論を言うとこれは医療費控除の対象になります。
国税庁のサイトに以下記載があります。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
ただし、見た目をよくするための矯正は医療費控除の対象になりません。
対象は医療費なので、治療目的でないとダメということですね。
還付金はいくら受け取れる?
上記の図の例では、医療費控除として申請した20万円×所得税率(20%)=4万円が還付金となりました。
日本では累進課税の制度を取っているので所得によって税率が異なってきます。
国税庁のサイトに掲載されています。
| 課税される所得金額 | 税率 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円 以上 | 45% |
制度として、医療費のうち10万円を超えた分が控除の対象となるので、
(かかった医療費-10万円)×所得税率
が還付金として返ってくる認識でOKです。
医療費控除申請のやり方
以下の国税庁のサイトから行うことが可能です。
確定申告というと混雑している税務署に行ってややこしい手続きを時間をかけて行うイメージがありましたが、やってみたら拍子抜けするほど簡単でした。
非常に親切・丁寧なお役所らしからぬシステムに仕上がっているので、説明に従って入力していくだけで済みます。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えばすべてオンラインで完結し、税務署に足を運ぶ必要はありません。
ただしマイナンバーカードが必要です。
医療費控除申請に必要な書類
子供の歯列矯正の医療費控除申請にあたって、実際に必要だった書類は以下でした。
- 源泉徴収票
- 領収書(歯列矯正の分)
- 医療費通知書(その他医療費の分)
ただし、いずれも書類のスキャンデータを登録したりということは必要無く、記載された金額等をシステムに入力していくだけです。
歯列矯正は健康保険の適用範囲外なので、健康保険組合から送られてくる医療費通知書に記載されないため、領収書を用意していました。
診断書等が必要になるのかと思っていたのですが、不要でした。
![]()
実際にやってみた
わたしはマイナンバーカードをちゃんと取得しているので、e-Taxで申請を行いました。
歯列矯正費用が約50万円かかったので、これだけで10万を超えていますが、その他にかかった医療費もまとめて申請しました。
医療費集計フォームというExcelファイルがダウンロードできるようになっているのでこれを使うと便利です。
確定申告をやったことがなかったわたしでも、30分ほどで完了することができました。
オンラインで完結し、税務署に足を運ぶ必要はありません。
カードリーダーはNTTコミュニケーションズのものがオススメです。
還付金額は8万円!
登録を進めていったら、最後に還付金額が表示されました。
86,530円!!
大金です!!
還付金は通常の申請で1~1.5ヶ月、e-Taxでの申請では3~4週間程度で振り込まれるようです。
還付金額8万円が確定!
申請はしたものの、本当に還付金がもらえるのか心配ですよね。
e-Taxで申請を行った場合、定期的に以下のようなメールが来るので、e-Taxのサイトにアクセスして還付金の処理状況を確認しましょう。
差出人:e-Tax(国税電子申告・納税システム)
件名:税務署からのお知らせ(○○ ○○様)【還付金の処理状況に関するお知らせ】
わたしの場合は毎週金曜にメールが来ていました。
そして、2/25(金)にメールが来てから確認したところ、以下のようになっていました。
「還付金の支払手続を下記の日程にて行います。」とあるので、無事に承認されたようです。
還付金が振り込まれた!
これで実証できました。

逆に、医療費控除を考慮に入れることで、子供の歯列矯正費用の実質負担額は小さくなります。
仮に歯列矯正に関する費用が50万円、所得税率が20%だとすると医療費控除申請を行うことで8万円が還付されるので、実質負担額は42万円ということになります。
歯列矯正をしてあげたいけど費用が高くて・・・と悩んでいる方は医療費控除も含めて考えてみると多少はハードルが下がるかもしれません。
それでも高額ではあるのですが。
医療費控除申請はいつやれば良い?
確定申告の期間は例年2月16日~3月15日となっていますが、医療費控除申請は扱いが異なります。
確定申告の中でも、払いすぎた税金が戻る「還付申告」については、前年の分を翌年の1月から申告することが可能です。
医療費控除も「還付申告」なので、その年の翌年1月1日から5年間は申告ができます。
つまり、2021年分の医療費については、2022年1月日から2026年12月31日まで控除申請が可能です。
源泉徴収票が届いたら早速申請を行いましょう。
確定申告期間中は税務署は超多忙となるので、できればその前に済ませたいところです。
日頃からやっておくべきこと
医療費控除申請なんて本来はしないで済むならその方が幸せなのですが、仏陀の教えのとおり人間は生老病死からは逃れられません。
もしもの事態に日頃から備えておきましょう。
- 病院の領収書は取っておく
- 源泉徴収票や医療費通知書等の重要書類も取っておく
後からこんな制度があったと知ったときに、必要な書類が無いでは残念過ぎます。
我が家では領収書保管用のファイルをリビングに置いており、ある程度高額の支払いが発生した時は領収書や関連書類を入れるようにしています。
源泉徴収票や医療費通知書も同じ扱いです。
上記のとおり申請期間が5年間あるので、過去5年分までさかのぼって申請することが可能です。
少しの手間で家計が助かるので、ぜひ検討してみましょう。
お金のことはプロに相談するのがオススメ!
お金や保険に関しては一度プロの意見を聞いてみるのがオススメです。
ライフプランの見直しもできますし、知らないと損するお得な情報が聞けたりしますよ。
わたしもファイナンシャルプランナーの方と相談したことでちょっと生活に余裕が出てきました。