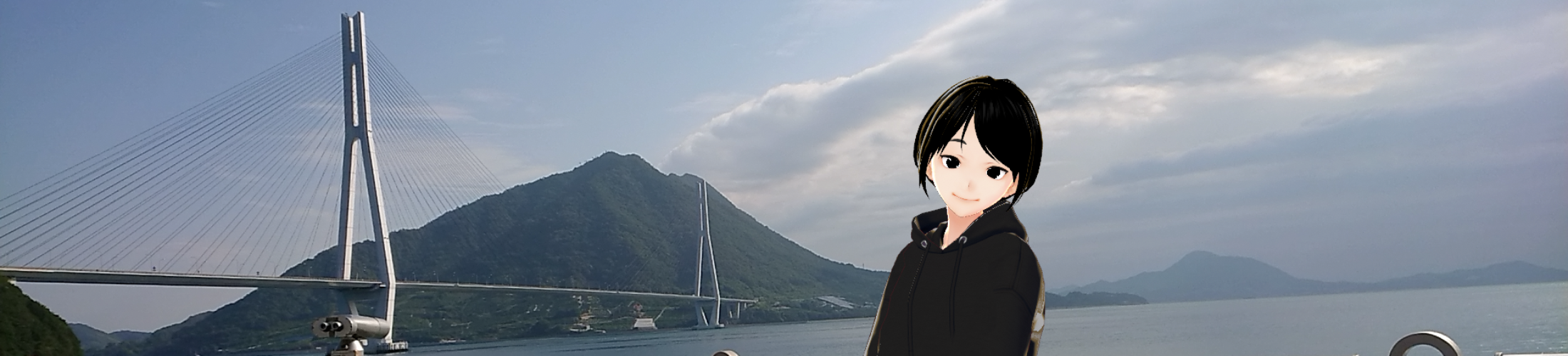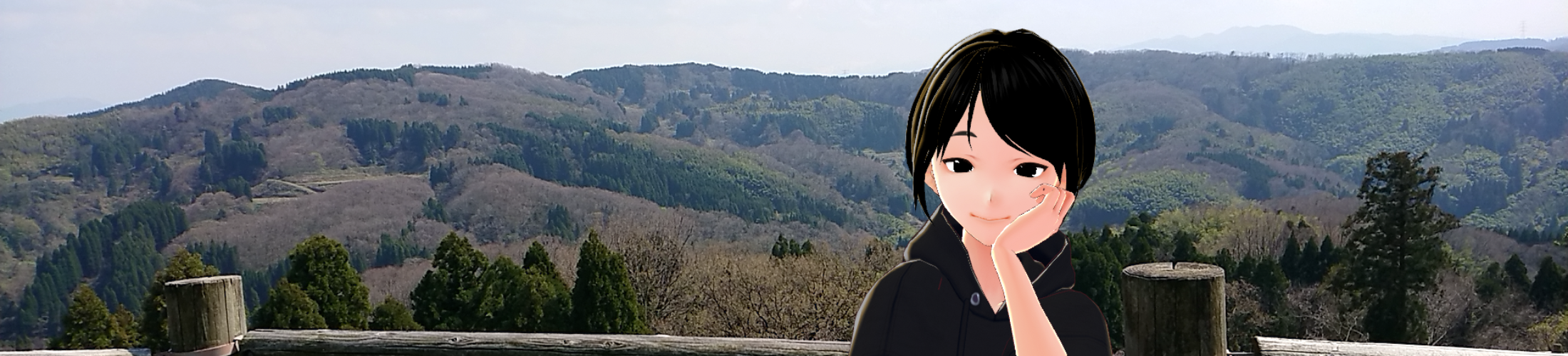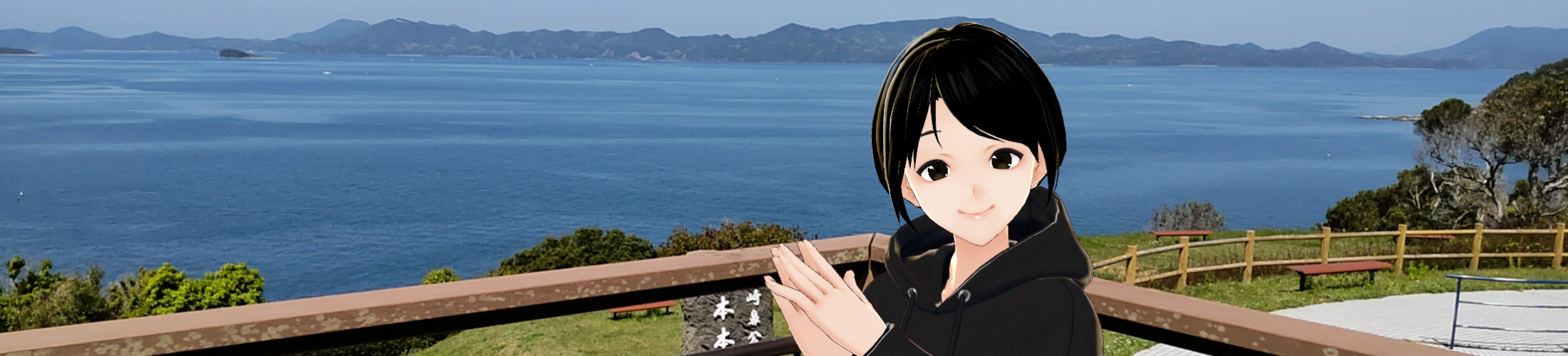車の運転を習うまでは、本当の“ののしり方”を知らない
―チャーノックおじいちゃんの法則
人生のどのタイミングでバイクに乗り始めるかは人それぞれあると思いますが、これだけは言っておきたい。

目次
理由は3つある
わたしは18歳の時に自動車の運転免許を取りましたが、バイクの免許を取得したのは35歳です。
都内在住時などほとんど運転していない期間もありましたが、バイクの免許を取得した時点でクルマの運転経験としては10年、20万km以上はありました。
今になって思うと、クルマの運転経験を十分に積んだ上でバイクに乗り出したというのは順番として非常に良かったと思います。
理由は以下の3つです。
- 公道に慣れる
- 危ない経験をする
- クルマからバイクがどう見えるかを理解する
順番に解説していきます。
①公道に慣れる
バイクの教習では公道に出ることは無く、自分でバイクを購入・所有したらいきなり公道デビューということになります。
これがクルマの運転経験があれば、公道という場を知っているので負担がかなり軽減されます。
公道は怖いと理解する
ある程度運転の経験を積んだ人ならわかると思いますが、公道では予想外の状況に遭遇することが頻繁にあります。
「かもしれない運転」を教習所で叩き込まれますが、すべての危険を予測することはできません。
クルマ、自転車、歩行者。それぞれ予測不能な行動に出ることがあります。
クルマにしてもバイクにしても、相当のスピードで走っているわけですから、ちょっとしたことで事故につながり、場合によっては人命に関わるということをしっかり理解しておかなければなりません。
公道でのマナー
公道では、車の流れや混雑度合い、路面状況、天候等の状況に応じた運転が必要です。
教習所では法規に則った走行を学びますが、残念ながらそれだけでは危険に満ち溢れた公道で生き抜いていくことはできません。
例えば制限速度40km/hの道路があったとしても、実際は50~60km/hくらいで流れているのが普通です。
そこを40km/h以下で走るのは、ルールは守っているけどマナーは守っておらず、周囲に迷惑をかけることになります。
周囲の車と速度差が大きい方が危険ですし、最近の傾向で言えば煽り運転を誘発することになりかねません。
逆に、(ある程度)ルールは守っていなくてもマナーは守っている方が実際は安全です。
車線変更、合流、交差点での譲り合い等、マナーが発揮される場面は多々あります。
この「ルールよりマナー」という感覚を、実際に公道を走っていく中で身に付けていく必要があります。
(法令違反を推奨するものではありませんよ。念のため)
クルマよりバイクの方がリスクが高い
クルマとバイクでは、(特にAT車が大半の現在では)バイクの方が操作が複雑ですし、ミスした場合のダメージ(転倒、負傷)が大きくなります。
つまり、バイクの方がより大きなリスクを抱えているということです。
例えば交差点で信号待ちから発進しようとした場合。
クルマだと、AT車はアクセルを踏むだけですし、MT車でもせいぜいエンストするくらいです。後続車からクラクションを鳴らされるかもしれませんが、身体には何の影響もありません。
これがバイクの場合、エンスト→立ちごけまで可能性があります。交差点を右折するときに転倒でもしようものなら、引き起こして再度発進するまでに他の車に轢かれる危険性すらあります。
危険な公道に初めて出るだけでもリスクが高いので、運転するものはリスクが低いものの方がよいと考えます。
②危ない経験をする
飲酒運転をするとかそういうことではないですよ。
運転中のいわゆる「ヒヤリハット」を経験し、どういう行為が危険に結びつくのか、どこに危険の可能性があるのかというのを心身に刻み込むということです。
(一番効果があるのは実際に事故に遭うことなのでしょうが、さすがにそれは…)
クルマの陰から飛び出してくる歩行者や自転車。
信号無視して突っ込んでくる自動車。
大型トラックの死角から現れるバイク。
西日や大雨で視界不良の際の運転。
こういったものを体験していく過程で、多くの罵詈雑言を吐くこととなるでしょう。
しかし自分も同じように罵倒されている可能性も同時に意識しておかなければなりません。
③クルマからバイクがどう見えるかを理解する
個人的に、これが最も重要です。
クルマを運転しているとバイクに対して思うことが多々あります。
まず、バイクの特性として車体が小さいため死角に入りやすいというのがあります。
死角から急にバイクが出てきて危なかったというのは、クルマを運転している人なら一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
このクルマ側からの視点があれば、バイクを運転する際に死角に入らないような、周囲に自分の存在をアピールするような運転が自ずとできるはずです。
また、バイクの運転、振る舞いについても思うところが出てくるはずです。
ぶっちゃけ、クルマから見るとバイクは良いイメージを持ちようがありません(自転車よりはマシですが)
自分がバイクを運転するようになった今は寛大な心で見れるようになりましたが、それでもイラっとすることはあります。
例えば、信号待ちや渋滞の際にすり抜けをされるのはいい気分ではありません。
ムダにエンジンを吹かして騒音をまき散らすのも不快です。
スピード狂も嫌ですが、原付(二種含む)がトロトロと車線の真ん中を走っているのも邪魔です。左に寄って譲れと。
こういう経験が、周りに迷惑をかけない運転につながるわけです。
要するに、自分がされて嫌なことはやるなってことですね。
クルマに乗ったことがないとこの感覚はわかりません。
ですが、公道の圧倒的多数はクルマなので、必要な感覚です。
まとめとお願い
以上のとおり、比較的リスクの少ないクルマで公道の経験を積み、公道でのバイクがどういう存在なのかを十分に理解してからバイクで公道に出た方が、安全で健全なバイクライフにつながります。
なので、バイクに乗るのはクルマの運転に慣れてからの方が良いと思うわけです。
もっとも、若人にはバイクから入る人も少なくないと思います。
経験豊富なおじさん方は、そういった若人に対して本記事の内容を踏まえてちょっとしたアドバイスをしてもらえればと思います。
もし娘がバイクに乗りたいと言い出したら
ちなみに、わたしの娘(現在小3)がいずれバイクに乗りたいと言い出したら、クルマの運転で1年間無事故無違反でいられたらという条件を付けるつもりです。
もっとも、誰に似たのか女子力が極めて高い娘なので万に一つも可能性は無いと思っていますけども。
バイクのトラブルに備えるにはJAFがオススメ!
バイクに乗る際は車以上に万が一のトラブルが心配ですよね。
なので、わたしはJAF会員になっています。
JAFは自動車のイメージが強いと思いますが、実はバイクのトラブルにも対応してくれるんですよ。
- バッテリー上がり
- パンク対応
- ガス欠対応
- 故障車けん引
これらの充実のロードサービスが全て24時間365⽇、何度でも、無料で対応してもらえます。
更に身近なお店(全国約39,000の会員優待施設)でJAF会員割引や優待が受けられるので、年会費は軽くペイできます。
お得に安心を手に入れましょう!