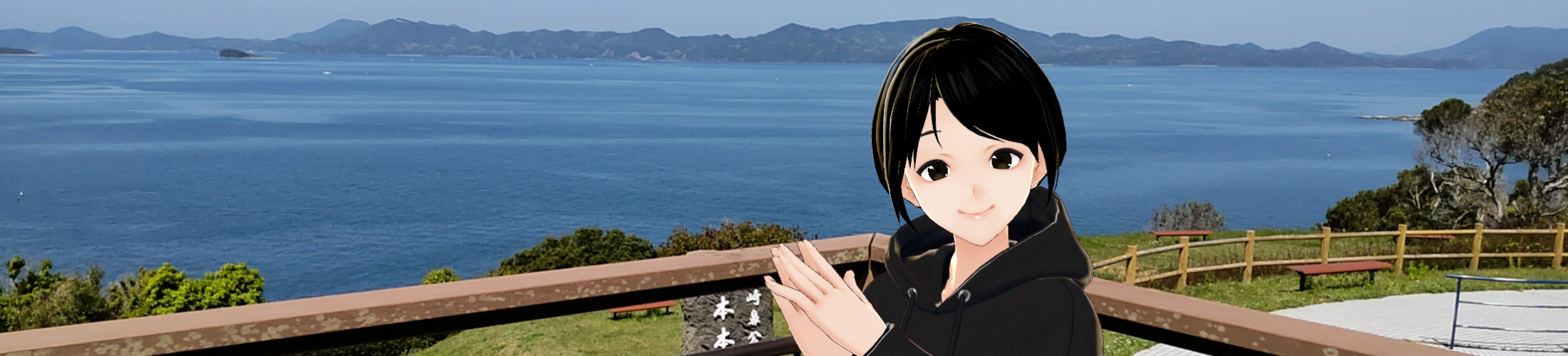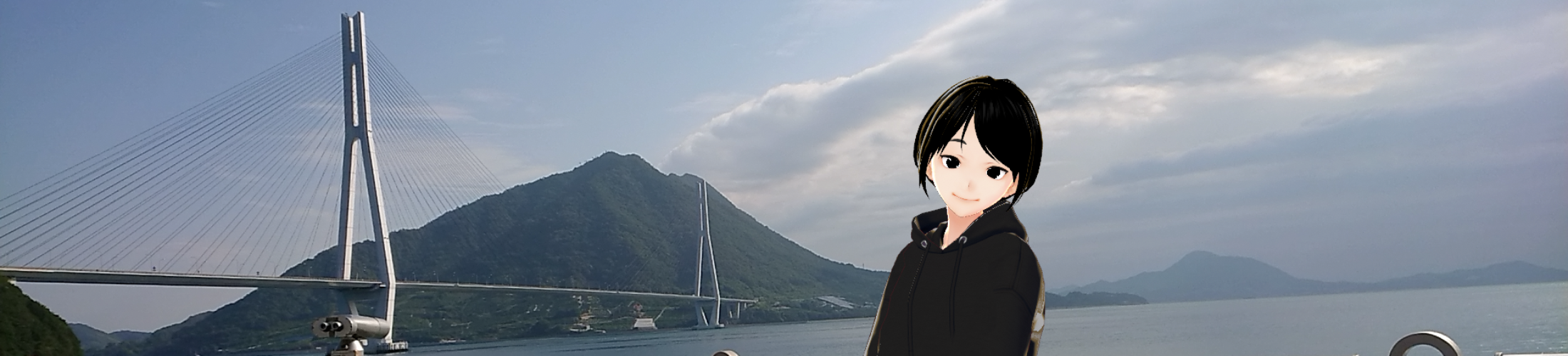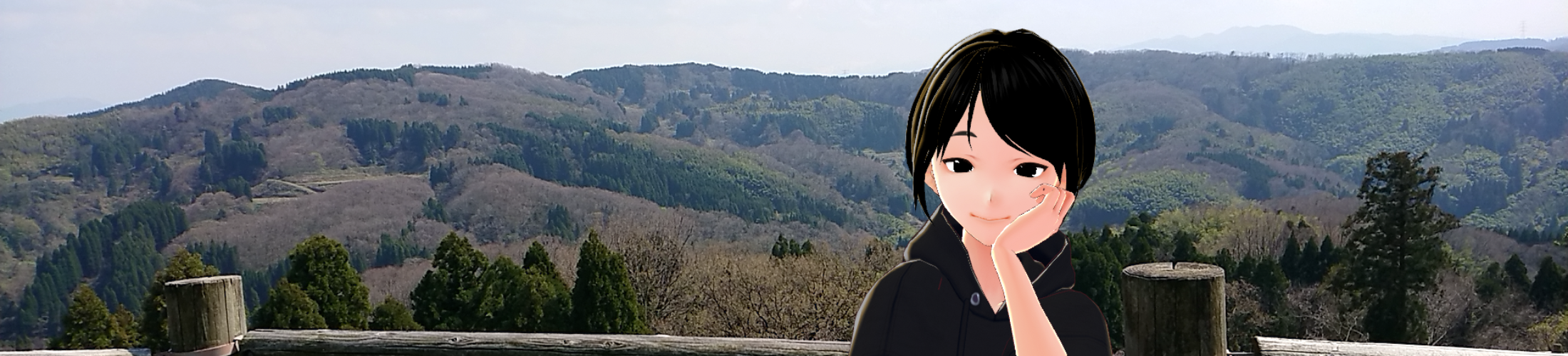バイクというものは、あえてそのままではちょっと足りないようにしている気がします。そのちょっと足りない部分をどう補っていくかというのが楽しみだし、個性の現れるところなんだと思います。
わたしも納車前からこういう感じにしたいなあというのがあったので、気が早いですが事前に取り付けたいパーツを用意していました。
どんな感じに仕上げていったのか紹介します。
バイクはちょっと足りないくらいがちょうどいい
バイクに乗っているとふとこんな風に思うことがあると思います。
もうちょっとスピードが出るといい。
もうちょっと荷物が積めるといい。
もうちょっと快適に走れるといい。
もちろん今でも最高に楽しい。でも、もっとよくできるんじゃないか、と考えてしまうんですよね。

補強ポイント
わたしがクロスカブ(JA10、初期型)に乗るにあたっての補強ポイントは以下です。
カブで日本一周したりロングツーリングに出たりしている人のブログ等を見ていたら自然とこうなりました。
- 積載性
- 電源
- 快適性
要するに、荷物を積んで快適に遠くまで走れるようにしたいということです。
ちなみにグリップヒーターだけは購入時に付けてもらいましたが、それ以外は自分で取り付けるつもりでした。
カスタムのしやすさがカブの良いところですし、せっかくだから自分でいじってみたかったんですよね。
ただ、バイクの基本機能である「走る」「曲がる」「止まる」に関わるところは安全性の観点から触れないようにしていました。
実際に購入したもの
初期段階で実際に購入して取り付けたものです。
カブのパーツ購入はAmazonでも可能ですが、アウトスタンディング・モーターサイクルがオススメです。
積載性強化
クロスカブにはマーラ様のようなご立派なキャリアが付いていますが、そのままでは使い勝手が良くないので補強が必要です。
![]()
アイリス箱
ドラフト1位はアイリスオーヤマのRVBOX 460。通称アイリス箱です。もう定番中の定番。
容量は30リットル。OGKのジェットヘルメットがすっきり入るので重宝しました。取り付けは荷締めベルトで。

メッシュインナーラック
手元の小物入れとしてすさまじい威力を発揮した、メッシュインナーラックです。
カブのレッグシールドをうまく利用した構造なので、クロスカブだとJA10専用。JA45以降に対応したものもあるようですが、見るからに小さくて実用性はイマイチそう。
グローブとかウエスとかペットボトルのドリンクとかを雑に突っ込んでいました。超便利。
電源取り出し
これは実際には納車後に買ったんですが、いずれ買うつもりではいました。
バイク用USB電源
スマホをナビに使うつもりでいたので、USB電源は必須でした。デイトナの2口のものを取り付け。
2口同時に使うことは無かったんですが、3年くらい経つと1つが接触が悪くなってもう1つの方を使うようになったので結果的には正解でした。

快適性向上
カブは素敵な乗り物ですが、いかんせん素の状態では無課金ユーザー並みにシンプルなので、いろいろ装備を増やしていきたくなります。
ウインドスクリーン
ウインドシールド、風防、いろいろ呼び方はありますが、要するに風を防ぐものです。
取り付けると一気にダサくなるんですが、実際あると無いとでは全然違うので個人的には必須装備です。
こちらもデイトナのものを購入。クランプバーを追加できるのが魅力でした。
時計
カブって時計付いてないんですよ。なので後付け。腕時計を巻き付ける人もいるようですがわたしはタナックスのコレ。
スマホホルダー
スマホナビ用に。最初に購入したのはこれですが、スマホ機種変の際にサイズが超ギリギリになってしまったので、RAMマウントのものに買い換えました。
スマホナビについてはコチラも参照してみてください。 バイクでツーリングに出かけるときにはナビが欲しくなりますよね。 最近はスマホをマウントしたバイクを見かけることも多くなりました。 本記事では、バイク用ナビを準備/運用する方法を経済性、利便性、安全性の ... 続きを見る

【中古スマホ】と【楽天モバイル】でバイク用ナビを無料運用する方法
ハンドルカバー
北陸の寒い冬でもバイクに乗るためには、いかに手を冷やさないかが重要です。
グリップヒーターを付けていたも、風が当たるとどんどん冷えていきまるで効果がありません。
そこで最強なのがハンドルカバー。これとグリップヒーターで、コタツが完成します。真冬でも油断すると熱いくらいになります。
まあ見た目はアレですが。

まとめ
っとまあこんな感じで最初からいろいろと取り付けていきました。
カスタムというほどではないですが、自分で自分のマシンを形作っていく過程が楽しいですよね。
この形もあくまで最初はこうだったというだけで、この後またいろいろと変わっていきました。
最初は素の状態で満足していても、すぐにちょっとアレが欲しいなあ、物足りないなあとなってくると思います。
そこをどう解決していくのか、それもバイクの楽しみの一つですよ。